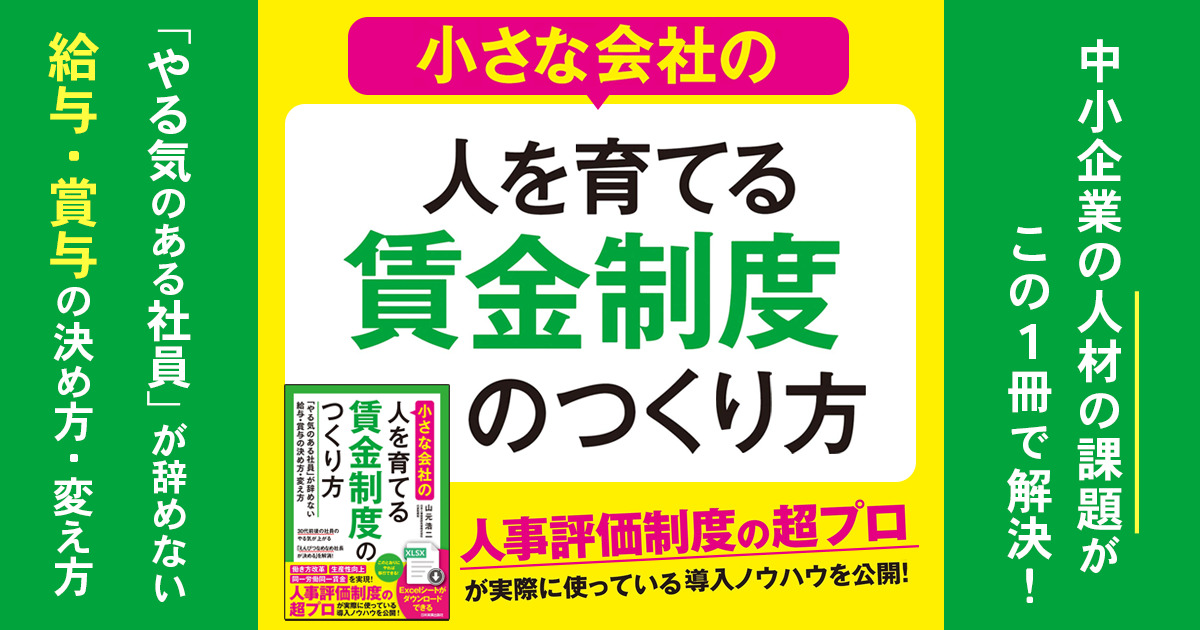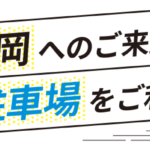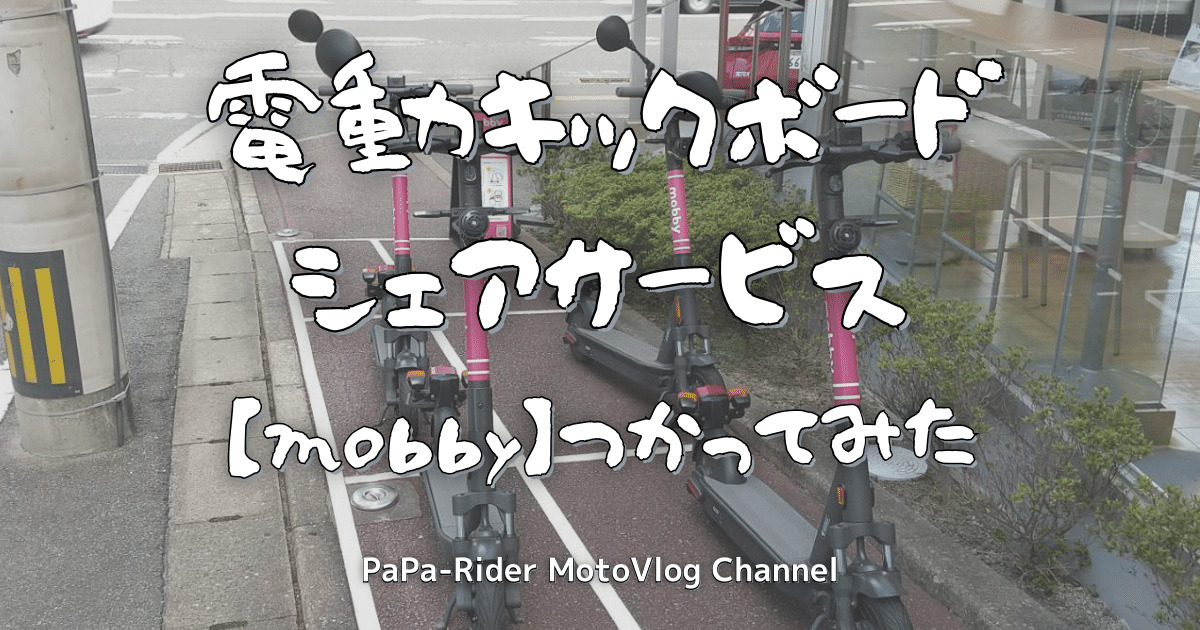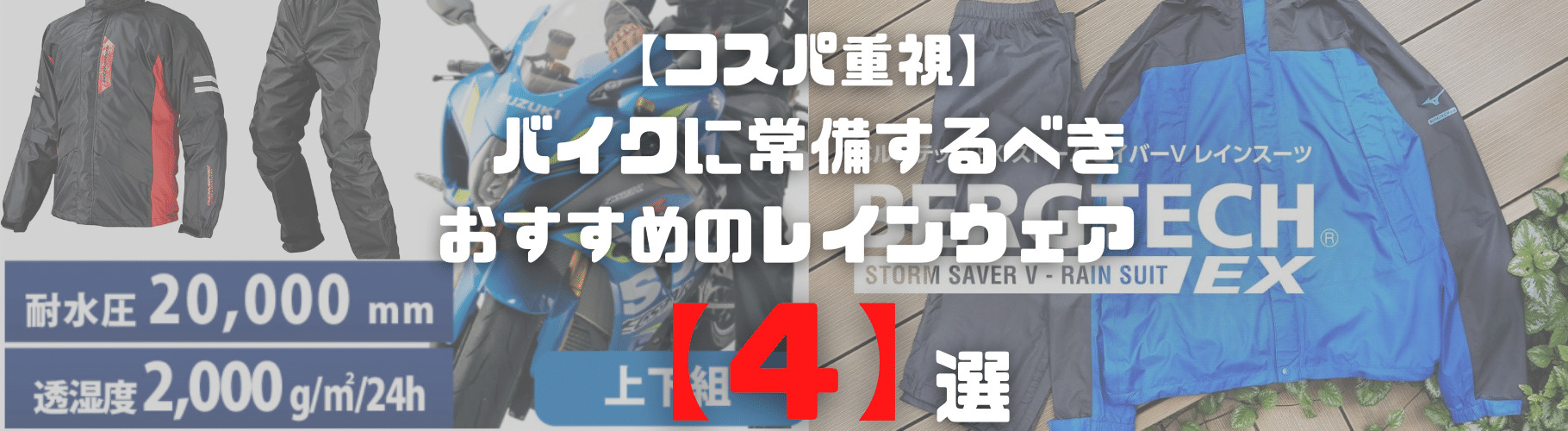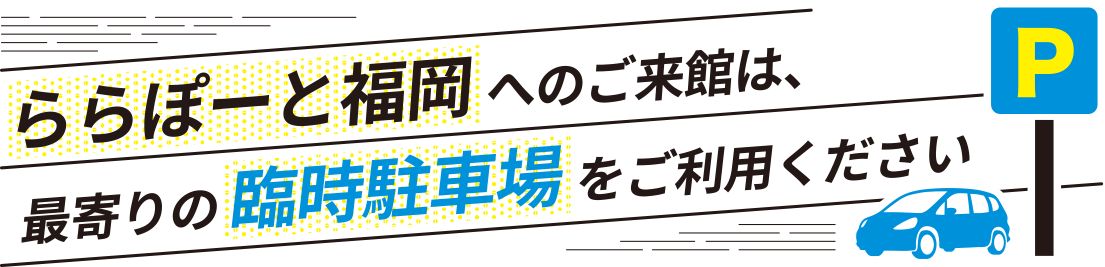中小企業と東証一部上場企業の平均年収には、およそ286万円(約1.8倍)もの差があることをご存じですか?
どうしてこんなにも差が開いてしまうのか。
それは、生産性に大きな差があるからにほかなりません。
小さな会社は生産性が低いため、人件費をあげることができないのです。
今回ご紹介する書籍はこちら!
【小さな会社の〈人を育てる〉賃金制度のつくり方 「やる気のある社員」が辞めない給与・賞与の決め方・変え方】
この書籍のテーマは『小さな会社の生産性をあげること』
人事評価制度や賃金制度の見直しを考えている経営者や人事担当者必見の1冊です。
中小企業の生産性に限界が生じる要因は何か

中小企業の生産性が上がらないのは、経営計画と人事評価制度がないことが原因です。
従業員1000人以上の大企業では、それらが明確で正しく運用されています。
『賃金制度』の刷新と導入をお考えの皆さんも、まずは『生産性を高めること』に注力しましょう。
人事評価制度を作ることができたら、給与や賞与の配分について社員の納得感を得るために、【リーダーの評価スキル】を高める必要もあります。
『生産性をあげる仕組み』 → 「経営計画」
『リーダーの評価スキル』 → 「評価制度」
これらの後に「賃金制度」を構築する。
「賃金制度」に対する誤解と3つの対処法

給料が上がって待遇がよくなれば社員のモチベーションは上がるはず!!
そんな風に考えていませんか?
確かに、賃金は少ないよりは多い方がいいですし、昇給した時の喜びは万人共通のものでしょう。
しかし、社員のモチベーションは一時的に上がるだけですぐにそれを当たり前と思うようになり、お金でしか動かない社員を作ってしまいます。
モチベーションというものは、賃金以外のところで上がることが多いため、『ビジョン実現型人事評価制度』の導入で社員に働き甲斐を、組織に成長をもたらしましょう!
誤解への対処法3選
- 賃金に対する不満を『評価制度』で解消
- 『経営計画』と『人事評価制度』で社員のモチベーションUPと成長を促す
- 働き甲斐を実感させられる組織づくりを推進する
『賃金』は社員の成長のバロメーターです。
社員の『経営計画』に対する貢献度と成長度を見える化する役割を持っています。
小さな会社の『給与設計』 4ステップ

- 『グレード』の段階数を決める
- 『グレード』の給与を決める
- 『役職手当』を決める
- 『基本給』を決める
STEP1 『グレード』の段階数を決める
『グレード』を決める2つの目的
- 社員の成長の質とスピードを高めること
- 5年後のビジョンと目標が達成できる組織を作ること
まずは、グレードごとに求める仕事のレベルを明確にしたうえで、それぞれのレベルに応じた給与を決めていきます。
グレードの例
スタッフステージ(Sステージ):一般社員
リーダーステージ(Lステージ):主任、係長など、管理職ではないリーダー
マネジメントステージ(Mステージ):課長、部長などの管理職
役職とグレードは別々にせず、それぞれに対応させておきましょう。
別々に運用してしまうと次のような弊害が生じてしまいます。
- グレードの仕事レベルと関係なく役職者が増える
- 上位グレードに低い役職者や、役職がないのに昇格してしまう社員が出てくる
- 評価の決め方と賃金への反映方法が複雑になる
グレードは、人材の成長ステップです。
本来は上位グレードに行くにしたがってリーダーシップを発揮しながらマネジメントができるようにならないと、組織は成長しません。
しかし実際には…
『勤続年数が長い』、『年齢が高い』というだけで役職を与えてしまう中小企業が後を絶ちません。
その結果
部下の育成能力やマネジメント能力の低い人材が部門長を務めることになり、若い世代が育たずに辞めてしまうのです。
これが中小企業の生産性が上がらない大きな要因であることは否定できません。
そのため、『グレード』の中にリーダーシップや部下育成など役職者としての必要な要素を盛り込みましょう。
そうすることで、そのスキルがない人の昇格はストップし、人材レベルに見合った給与を支払うことで無駄に払いすぎていたコストを削減することができます。
- S1 新入社員レベル
いわれたことを忠実に実行できる - S2 平社員レベル
担当業務を一人前にこなせるようになる - S3 主任レベル
後輩へのアドバイスや業務改善の提案ができる - L1 係長レベル
グループの目標達成に向けてメンバーに対し的確な指導とプロセス管理ができる
プロジェクトの実行推進や進捗管理ができる
メンバーの育成を安心して任せられる - L2 課長・部門長レベル
部署の戦略やアクションプランの立案ができる
アクションプランの実行推進や進捗管理ができる
部署の予算の把握や目標達成へ向けた指導ができる
コスト管理ができる
必要資格を取得している(2級資格程度) - M1 部長レベル
経営理念を部門全体へ落とし込むことができる
将来のビジョンを構築し、環境変化に対応できる
問題・課題を早期発見し、対策・解決ができる
必要資格を取得している(1級資格) - M2 本部長・事業部長レベル
事業部全体に対し、経営理念の方針や目標の立案、浸透・落とし込みができる
事業部全体の業務進捗状況の把握、指導、管理ができる
顧客の信頼を獲得し、業務の拡大を推進できる
STEP2 『グレード』の給与を決める
固定給の賃金構成は、基本給(本給+仕事給)、役職手当に分かれています。
各グレードの標準賃金をざっくりと考えてみましょう。
| M2 本部長クラス | 60万円 | 50~65万円 | 振れ幅15万円 |
| M1 部長クラス | 45万円 | 40.5~49.5万円 | 振れ幅9万円 |
| L2 課長クラス | 35万円 | 32.5~40万円 | 振れ幅7.5万円 |
| L1 係長クラス | 29万円 | 27.5~32万円 | 振れ幅4.5万円 |
| S3 主任クラス | 25万円 | 23.5~27万円 | 振れ幅3.5万円 |
| S2 一般社員クラス | 22万円 | 21~23万円 | 振れ幅2万円 |
| S1 新入社員クラス | 20万円 | 19.5~20.5万円 | 振れ幅1万円 |
STEP3 『役職手当』を決める
役職手当を決めるときには、仕事に対する責任の重さや範囲が広がるにもかかわらず手取り額が下がるなんてことがないように配慮しましょう。
具体的には、時間外手当の支給から外れる「管理職」の役職手当は、非管理職の時間外手当を完全に上回るように設定します。
役職手当
- 主任:1万円
- 係長:2万円
- 課長:5万円
- 部長:10万円
- 本部長:15万円
STEP4 『基本給』を決める
基本給は、先述の通り『本給』、『仕事給』、『役職手当』の3つに分解できます。
本給は、勤続給的に積み上げ支給がなされます。グレードごとに上限額・下限額を決めておきましょう。
仕事給は、成果や貢献度に応じて半年、または1年に1度変動させるのが一般的。
本給と仕事給の金額を決めるために、それぞれの割合は何を重視するかによって決まり、安定志向なら本給の、成果主義なら仕事給の割合が大きくなります。
それぞれの金額は、各グレードに対応した標準金額から役職手当を引いて、比率を掛けることで求められるので先ほど算出した標準金額と役職手当をもとに計算してみましょう。
| グレード・役職 | 基本給 | 本給(8割) | 仕事給(2割) | 役職手当 |
| M2 本部長クラス | 60万円 | 36万円 | 9万円 | 15万円 |
| M1 部長クラス | 45万円 | 28万円 | 7万円 | 10万円 |
| L2 課長クラス | 35万円 | 24万円 | 6万円 | 5万円 |
| L1 係長クラス | 29万円 | 21.6万円 | 5.4万円 | 2万円 |
| S3 主任クラス | 25万円 | 19.2万円 | 4.8万円 | 1万円 |
| S2 一般社員クラス | 22万円 | 17.6万円 | 4.4万円 | |
| S1 新入社員クラス | 20万円 | 16万円 | 4万円 |
仕事給は、評価ランクに応じて7段階(E,D,C,B,A、S,SS)で評価するのが一般的です。
先ほど定めた仕事給の基準をBランクとして、差額が均等になるように設定します。
本給と仕事給の割合が5:5であれば本給も同じ金額。
どんな割合で設定するのが自分たちの会社にあっているのかよく検討しましょう。
給与移行手順とノウハウ

現行給与の具体的な移行方法を解説します。
まずは社員全員のグレードを決めましょう。
ここでは、本人に求めたいグレードに設定します。
現行の役職の中での中途半端な名ばかり役職は整理してしまいましょう。(課長代理や担当部長など)
グレードを決めた後は、トライアル評価を3回以上行うことで不満やモチベーションの低下を防ぐことができます。
※組織の技術力アップに貢献する人材(マネジメントには不向き)は、『専門職』として育てると効果的。
マネジメントのラインとは別に専門職専用のプロフェッショナルラインのグレードを設ける会社もあります。
次に支給項目別金額の設定です。
固定給 ー 役職手当 = 本給支給範囲内 になればOK
はみ出した場合は調整給として後々つじつまを合わせていきます。
新体系に収まりきれない(調整給が発生する)社員については、調整給を残すかどうかを検討し、必要に応じて給与テーブルを再調整しましょう。
社員のやる気を引き出す『賃金制度』運用のコツ

本給の運用方法
給与改定のタイミングは年1回、あるいは昇格・降格したタイミングとします。
改定時期は決算月の翌月で、昇給方法は毎年定額加算です。
※ただし、売り上げや利益目標を達成することが昇給の条件。利益がないのにコストを増やすわけにはいきません。
昇給額の目安は固定給の1%がB評価。
E評価なら昇給はナシ、SS評価ならB評価の2倍、その他の評価では差額が均等になるように振り分けます。
仕事給の運用方法
仕事給改定のタイミングは、年2回および昇格・降格のタイミングとします。
改定時期は決算の翌月、半期終了月の翌月がベスト。
昇給方法は評価に基づき、下がる可能性もあることを覚えておきましょう。
改定のタイミングを年2回にしているのは、1度下がっても半年後に挽回できるチャンスが残っているからです。
挽回の可能性、もしくは仕事給が下がってしまう可能性があることで、社員は生産性をあげて業務に取り組みます。
調整給の扱い
調整給は、現状の給与と新しい評価・給与制度の間に生じた誤差のようなものなので、最終的になくなるように運用していきます。
具体的には以下の3パターンが考えられます。
- 昇給時に昇給額と相殺する
- 調整給の保証期間を定める(2年後に0になるなど)
- 調整給の減額基準を定める(半年後に半額になるなど)
すべてを組み合わせて早い段階で調整給をなくしてしまうのがいいでしょう。
賞与の支給基準の設計と運用方法
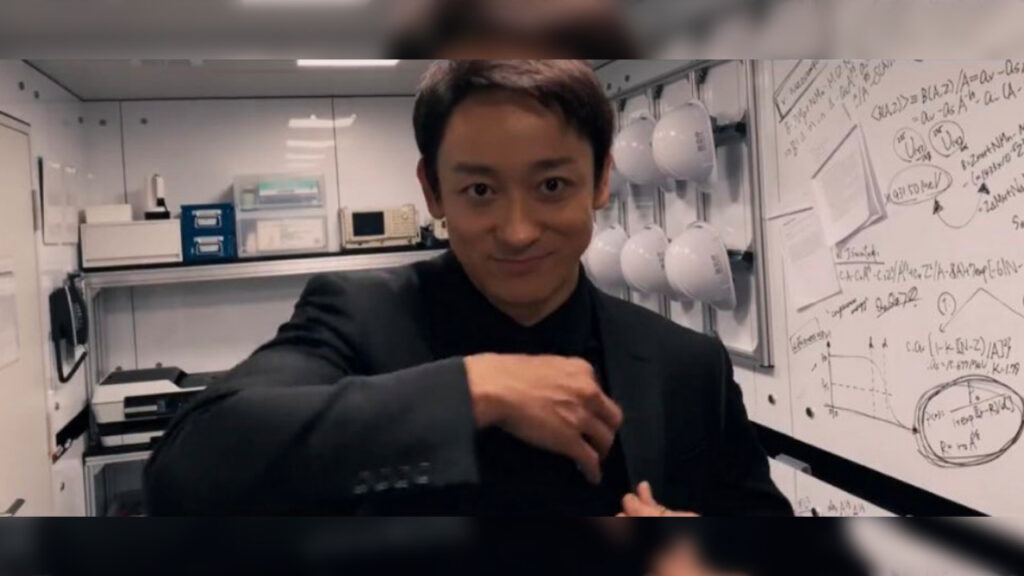
賞与(ボーナス)、私の好きな言葉です。
しかし、賞与では実はモチベーションは上がりません。
それは、もらえて当然だという認識を持った従業員が多くいることが原因。
彼らには賞与の位置づけと考え方が正しく認識されていないのです。
『賞与とは、会社の業績に応じて支給総額が決まり、評価によって分配されるものであり、支給額は毎回変動するもの』
また、賞与のルールが明確化されていないのも原因の一つ。
賞与の額は評価によって決定されますが、社長が独断で決めている会社も多く、勤続年数や年齢で仕事の評価や実績によらず支給されることがあります。
本来評価は各セクションのリーダーに任せるべき仕事です。
評価の部分をリーダーに一任しなければ、マネジメントのできるリーダーは育ちません。
『賞与支給基準』を就業規則に明記し、全社員に周知した上でリーダーには部下の評価を任せましょう。
賞与が社員のモチベーションにつながらない最後の理由は、自分がどういう評価を受けているのかがわからないということです。
仕事に対する評価、賞与の査定は面談を通して本人にしっかりと伝えましょう。
賞与は評価によって差がつくものなので、評価結果と判断理由をきちんと伝えて本人に納得感を持たせることが大切です。
賞与支給基準の作り方

賞与の総支給額を決める
賞与の総支給額の決め方は、経常利益の 〇% や、全社員の固定給総額×目標達成割合に応じた掛け率などで算出するのが一般的です。
経常利益から算出する場合、経常利益額を100%とし、それを『社員へ還元(賞与)』、『将来への投資』、『納税に必要な資金』、『会社に残すお金』、の4つに均等に分けた25%とするのが従業員への説明がわかりやすくなります。
賞与を全社員に分配するルール
≪賞与 = 賞与ポイント × ポイント単価≫
賞与の支給額は、上記の計算式で算出します。
賞与ポイントは、被評価者のグレードと評価で決まるので賞与ポイント表をしっかりと設計しましょう。
※グレード間、評価間格差の2軸で検討。
≪ポイント単価 = 賞与総支給額 ÷ 全社員のポイント合計≫
ポイント単価は賞与の総支給額を全社員のポイント合計で割ることで算出します。
「会社の業績」と「自分の評価」の2つの要素で賞与の額を計算することで、各社員が会社の利益と自分の評価をあげるために生産性高く、効率的に動くように仕向けましょう。
賃金制度で成果を出すために必要な5つのステージ
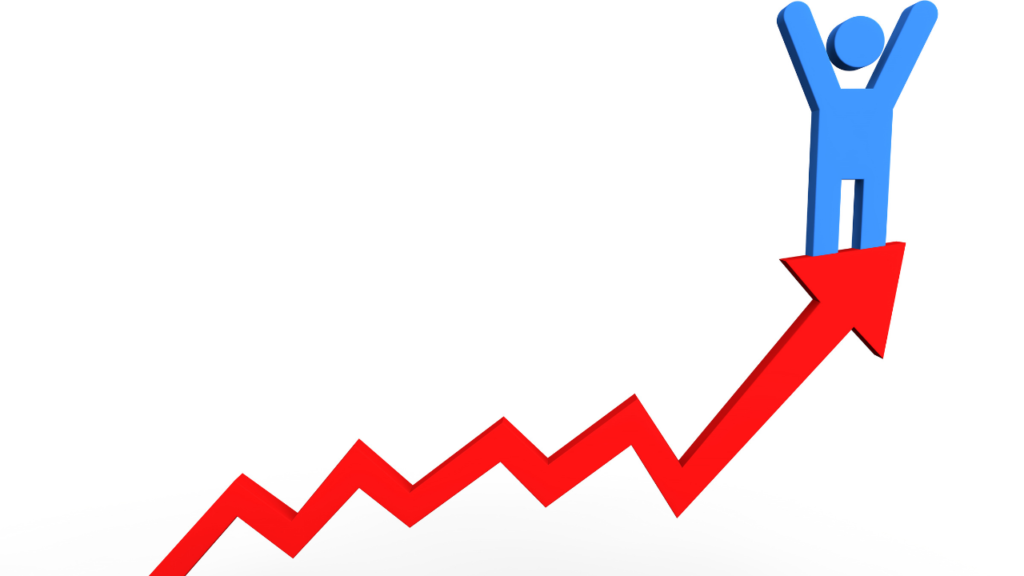
中小企業のリーダーに欠けている2つの力
- 部門をマネジメントする力
- 部下を育成する力
この2つの力を補い、組織を成長へと導く人事評価制度があります。
それが『ビジョン実現型人事評価制度』です。
『ビジョン実現型人事評価制度』は、次の5つのステージに分かれます。
- 経営計画を策定
- 評価制度の構築
- 評価制度の運用
- 経営計画の運用
- 賃金制度の設計
『経営計画』の策定
経営計画の策定には以下10個の要素が必要です。
【理念】ブロック
①経営理念 ②基本方針 ③行動理念 ④人事理念
【目標】ブロック
⑤ビジョン ⑥5か年事業計画 ⑦戦略
【人材育成目標】ブロック
⑧現状の人材レベル ⑨5年後の社員人材像 ⑩ギャップを埋めるために必要な課題
【理念】ブロックでは、『人事理念』をもとに社員を育成し、全社員が『行動理念』に沿って行動できるようになると、会社が『基本方針』通りに動いていることになり、『経営理念』に向かって会社が進んでいきます。
【理念】ができたら、『ビジョン』を掲げて『5か年事業計画』を打ち出し、目標達成のために『戦略』を練りましょう。
【目標】が定まったら、【人材育成目標】を明確にして理想の人材を育てます。
『現状の人材レベル』を分析したうえで『5年後の社員人材像』を定め、現在の人材レベルとの『ギャップを埋めるために必要な課題』を明示することで経営計画の策定は完了です。
評価制度を作る
評価制度を作るときには、「経営計画」を制度に落とし込みましょう。
経営計画で策定した「5か年事業計画」に沿って、社員全員が目標を意識できるようにします。
業績数値目標から会社の目標達成のために必要な項目を評価基準の『業績評価項目』に設定しましょう。
これは、全社員が目指すべき数値目標を明確にし、いつも意識しながら仕事に取り組むことによって目標達成に結び付けていくためです。
※全社、部門、個人の3つの視点で作成しましょう。
→全社員が会社や部門の業績を常に意識しながらチームワークを駆使して行動する組織が出来上がります。
人材を育成する
経営計画で立案した『戦略』に沿って、成果を出せる人材を育成しましょう。
『ギャップを埋めるために必要な課題』で必要な能力を身に着けた理想の人材を作り出します。
その時、能力評価項目として『評価基準』を設けましょう。
例:『報連相の徹底』、『業務の改善、提案能力』、『スケジュール管理』、『部下育成能力』など。
『行動理念』は『評価基準』に落とし込み、全社員で会社の考え方を実践します。
※『行動理念』は『経営理念』を実現するために全社員が実践すべき重要な視点。
自社の『基本方針』の実行につながっているかを、『評価制度』を運用しながら確認し、内容を改善、成果を高めます。
部下育成ができるリーダーを育てるための5ステップ
評価者(リーダー)は、『評価制度』を運用して部下を育成を任されることで、部下を育成・指導する能力が身に付きます。
部下育成ができるリーダーを育てるための『評価制度』運用方法を5つのステップに分けて解説します。
STEP1:評価の実施
リーダーが評価基準に基づき、部下の評価を行います。
部下自身にも、自分の行動を振り返り、自己評価させましょう。
※評価は必ず「本人」、「直属の上司」、「さらにその上の上司」の三者以上で行うこと。
『行動評価』はA・B・Cの3段階評価、『業績評価』はE~SSの7段階評価です。
STEP2:育成会議
評価点を集計し、評価結果を1枚のシートにまとめます。
これをもとに評価者同士で議論したうえ、相違点を統一、評価を決定してください。
この時、評価者同士の議論は「直属の上司」、「その上の上司」、「社長や人事担当社員など」の3社以上で行ないます。
社長や人事担当社員が主導して上司二人の意見のバラツキをそれぞれの判断理由をもとに統一。
評価を決定し、次回の評価までにチャレンジしてもらう目標を共有します。
STEP3:育成面談
次の成長に向けた目標をリーダーと本人で共有しましょう。
※必ず面談前に「面談育成シート」を作成して面談ストーリーを文章化したうえで実施してください。
面談では、上司2人が同席したうえで直属の上司がメインで進行しましょう。
最後に、次回の面談までに達成するべき成長目標を3つ決めて共有しておきます。
STEP4:成長目標設定
〔STEP3〕で決めた目標をもとにそのレベルと達成までのプロセスを決めます。
※目標は3つに絞り、どこまでやるのかゴールを明確にしてください。
実行手順は具体的に明確化し、いつまでにどういうプロセスで実行するのか計画を立てましょう。
STEP5:チャレンジ面談
リーダーは、〔STEP4〕で決めたプロセスの進捗状況、達成度を確認して情報を共有し、アドバイスを行いましょう。
※直属の上司が主導となり、毎月実施すること。(面談は10分程度とします。)
毎月「チャレンジシート」を作成して面談スケジュールを立て、面談日時も事前に決めておきます。
この5ステップを回すことができるようになれば、リーダーとして必要な部下育成指導力が身についたと言えるでしょう。
『経営計画』を実現するプロセスは『戦略』として『経営計画』に明記されています。
その運用をリーダーに任せることで部門マネジメントができるリーダーが育つのです。
まとめ
『戦略』を立案しただけであとはリーダーにお任せ。
そのような企業はたいてい失敗しています。
リーダーは、『戦略』を実践に結び付ける手法や管理を学んでいないからです。
『経営計画』の運用、『アクションプラン』の推進によって、プロセス通りに実践していくことで、『戦略』を推進するときのポイントや手順とその管理方法について、リーダーは学ぶことができます。
『アクションプラン会議』が『戦略』を成功に導きます。
社長やリーダーがアクションプランの進捗確認や改善を推進しましょう。
※『アクションプラン会議』は毎月開催してください。
各アクションプランの担当者から前月の実行状況や課題の報告を受け、参加者全員で共有したうえで進捗をサポートするのがリーダーの仕事です。
実行できているものに関しては効果検証を必ず行い、効果を高めるための改善もみんなで意見を出し合います。
自らこれらを推進できるリーダーとなれば、安心して組織運営を任せられるはずです。